20181004 室堂 カヤクグリ ミヤマハンノキ 食事
今朝の室堂は曇。
やや視界良。
ライチョウ君予報士としては、むつかしい予測。
1羽の♂のみですぐに見えなくなってしまいました。
昨日の鳥果からです。
ミヤマハンノキの実が歩道脇に落ちて、カヤクグリ君の朝食でした。
カヤクグり君は室堂MKB48のメンバーでセンターはライチョウ君ですが前列で頑張
っています。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
果実は3~4mmほど。翼がついていて、風で遠くへ運んでもらう設計です。
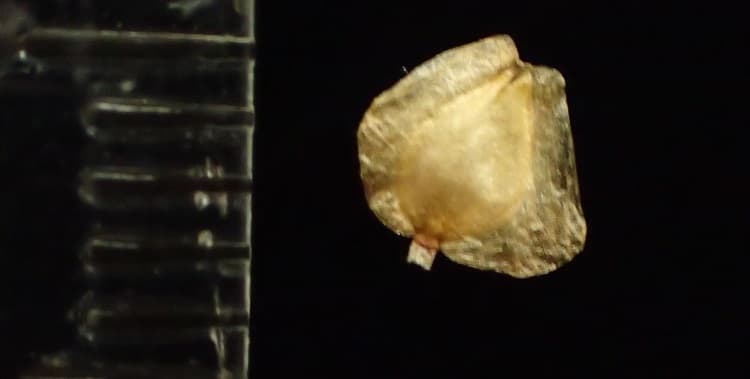
OLYMPUS DIGITAL CAMERA






カヤクグリ君のミヤマハンノキの食事初動画です。(^^♪
byハイマツ仙人
↓























